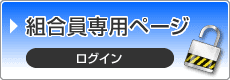湯も・北たコラム
委員長湯本憲正と書記長北原隼人が書き込む湯も・北たコラム(旧「ノリ・スケだより」)
5月30日 第58回現業協議会定期大会開催
大会では、昨年の活動の総括を踏まえて、新年度方針を確立し、森泉議長以下三役の再任が決定されました。
◆中央執行委員長あいさつ
県職労現業協議会の第58回定期大会に参集されました代議員、現業協役員の皆様大変ごくろうさまです。
この4月より県職労中央執行委員長を務めております湯本和正です。大会の開催にあたりひとことごあいさつを申し上げます。
日頃から森泉議長を中心に現業協議会の運動をはじめ、県職労の運度の先頭にたって取り組んでいいただいておりますことに改めて感謝申し上げます。
昨年、長野県は多くに自然災害に見舞われ、ここ木曽の地は7月9日の大風8号による土石流災害、9月27日の御嶽山噴火災害により人的・物的に大きな被害が出ました。風評被害を含めるとこの災害による損失は計り知れないものがあり、大会がここ木曽の王滝村で開催されることは執行部による地域応援の趣旨もあると聞き深い敬意を表する次第です。
私たちを巡る様々な情勢についてはそれぞれの皆さんが認識されていることと思いますので、別の機会に触れさせていただくとして、現業協議会を巡る課題等に絞って触れ、あいさつとします。
さて、2009年のいわゆる「大枠合意」から2014年度までの任用替え希望者の全員合格を経て、実質的に県職労組織としては現業職員が存在しないこととなりました。そして、大枠合意によって当局の民間委託の提案は堰を切ったように行われてきています。
県当局からの現業職場の民間委託の本格的な提案は、私の本部書記長時代で1998年10月に事前協議のあった「長野盲学校の給食業務の民間委託」でありました。2000年1月の妥結まで、地公労による組合組織内での取り組みに止まらず、県民へのアピールなどの取組みや業務に対する法的問題点の学習など、様々な取り組みを行い、民間委託は阻止できなかったもののその後の運動の原点を築いてきました。
また、その当時から自治労本部が提唱した「現業活性化」の取組みの必要性を現業協議会をはじめ組織内全体に説いていたことを覚えています。現業職場の民間委託の流れに対抗する取り組みとして位置づけてきたものですが、当時を思い起こすと、“こんなことができるのか”、“いまさら何だ、このまま静かにしておいてほしい”など、この取り組みに対する組合員からの懸念を示す意見も多く聞かれ、それを払拭するための私の論理に現業協組合員からは“当局の回し者”、“お前はどちらの立場なのだ”と揶揄され、叱責されたことも覚えています。
今日に至っても現業という職種に対する差別的意識があることは否定できませんし、当事者にあっても現業職に対して負い目を感じている組合員もいることも事実です。このような意識の改革を進めることこそ現業活性化の取組みであると考え学習してきたものと考えています。
任用替えが行われた現時点においても当事者は無論、周りの意識は様々であると認識しています。“もう現業職員ではないから機関紙は配布しないでほしい”“現業協議会から抜けたい”などの意見も聞く一方で、任用替え後職場に馴染めないことからメンタル的に厳しい状況に陥ってしまっている組合員や退職してしまった組合員など、さまざまな反動があります。
このことは、任用替えした当事者ばかりでなく、職場で支えるべき立場の組合員側においても認識していかなければならないものと考えています。
人である以上様々な考え方があることは否定できません。また、仕事、職場が一変して対応に苦慮されていることも理解できます。しかし、現業職場は依然として存在し、これまで担ってきた職員がそこに存在していたことは紛れもない事実です。
県民のためにより良いサービスを提供していくことは私たちの使命であり、現業、非現業の枠を超えて実現しなければならないことです。
また、個人的課題は一人の人間として現況を乗り越えてこそ展望が開けることを確信していくことが必要です。そして、基本組織の組合員も含めたフォローアップをしていくことも欠かせない取り組みです。そこに引続く現業協議会の存在意義があり、支える県職労があるものと確信しています。
任用替えしたことによる個人的な利益と不利益(負担)の両面が入り乱れている時期です。
現業の職種の必要な職場もいまだ存在することも事実です。現場のことは現場が一番わかるのであり、その自負と確信をもつことが対当局に対する圧力となると言えます。
本来の現業職場の存在意義や公共サービスのあるべき姿論は、行財政改革という自治体内部のコスト論のみに矮小化されたものによって打ち出された施策であったといえますが、直営堅持の取組みは時代という大きな流れに対抗できずにきました。
結果論は受け入れ、これからの現業職場の維持改善と関わってきた組合員、職員の処遇改善を最大限取り組むことが肝要です。
最後に県職労全体にかかる賃金労働条件の改善に向けた課題について述べます。
政府自民党の策動による「給与制度の総合的見直し」が行われました。2005年の給与構造改革に引続く改悪は、またもや高齢層職員や高位号俸者がターゲットにして給与水準は下がる一方です。
意欲を持って職務に精励できる処遇と賃金は不可欠でありますが、逆行するものです。当面現給保障が3年間行われますが、長野県の給与実態を追及しつつ対人事委員会対策を強化するとともに、2016確定での継続課題を中心に交渉協議による要求前進をはかります。
また、現業職場では試験研究機関の新たな雇用・行政嘱託員に関する事項も課題といえます。現場の生の声を聴くことが何より重要と考えています。
様々な課題がありますが、本大会の論議を経て長野県職労現業協議会の構成組合員の意思疎通が図れ、相互理解のもとに直面する様々な課題に一丸となって取り組まれることを期待して県職労本部としてのあいさつとします。
ともにがんばりましょう第86回長野県中央メーデー
◆中央執行委員長あいさつ内容
5月25日 第60回青年女性部定期大会開催
◆大会における中央執行委員長のあいさつ内容
運動を支えた青年女性のちからをこれからも
○今国会のふたつの大きな課題
反戦・平和の推進と労働法制改悪阻止
ひとつめは反戦・平和の取組みです。「特定秘密保護法」「集団的自衛権行使容認」「辺野古移設」「オスプレイ」「安全保障法制」などは、毎日耳にするキーワードです。
○長野県の給与水準の向上と労働条件の改善をめざして
課題を共有してまず声を挙げよう
給与カットは地方交付税を人質にして給与カットを強要し、総合的見直しは、本来労働基本権制約の代償措置であり、第3者機関として存在する人事院への圧力によって地方波及を狙った介入を行いました。
3月25日春闘要求回答交渉
3月25日、15時から県庁西庁舎110号会議室で、春闘要求回答交渉を行いました。交渉団は20名余。春闘要求書は、2月17日に提出交渉を行い、3月13日付けで文書回答があり、今回、回答交渉を実施したものです。事前協議制など従来からの労使間ルールを守る、人事委員会勧告の尊重、交渉・合意事項の書面協定化等について当局の考え方を質し確認しました。加えて、超過勤務の縮減等に努力していく当局側の姿勢も確認しました。これら、春闘期における基本的事項の確認ができたことから交渉を終了しました。また、この日で今年度の交渉は終了しました。現在の執行部メンバーでの交渉は最後でした。この間、ごご支援・ご尽力いただいたすべての組合員の皆さんに感謝申し上げます。
3月11日新役員決まる
3月11日、投票管理委員会が開催され、全組合員を対象に3月9日に実施された次期役員に対する信任投票の開票が行われました。その結果、湯本和正中央執行委員長を始め、執行部・監事の全員が信任されました。任期は、2015年4月1日から2年間となります。なお、現執行部から、北原委員長、中野副委員長、小平・北原中執が退任しますが、他の役員は再任となります。引続き県職労運動前進のため奮闘いただきたいと思います。得票数等は速報でご覧ください。