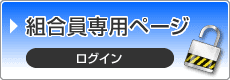湯も・北たコラム
委員長湯本憲正と書記長北原隼人が書き込む湯も・北たコラム(旧「ノリ・スケだより」)
3月4日36協定に関する交渉
交渉など
2月17日、地公労共闘会議と県本部で人事委員会事務局に対して申入れを行いました。例年この時期に行っており、人事委員会に対して基本的事項を要請しました。人事委員会はご存じのように第三者機関であり交渉相手ではありません、当局ではありませんが要請書(ときには要求書も)を提出して組合側の考え方を説明し、理解されるよう取り組んでいます。要請に対して事務局長は、「要請内容は人事委員に伝える。民間給与実態調査については、今のところ従前と同じ方法、スケジュールで準備を進めている。これまでどおり公正・中立の専門機関としての役割を果たしていきたい。」とした趣旨の考え方を示しました。今後も勧告までの間、随時要請行動等を実施していくつもりです。自民党による地方公務員給与削減の動きに対しても自治労本部を先頭にしっかり取り組む必要があります。
同日、県当局に対して春闘要求書を提出しました。事前協議制、交渉し合意した事項の書面協定化、賃金、人事委員会勧告の尊重、人員配置、超過勤務等について基本的な事項を要求しました。3月25日に回答交渉を行います。
さらに同日、36協定の締結に関する交渉を実施。当局とは2014年に36協定に準じた内容の「時間外及び休日勤務に関する基本確認書」を取り交わしていますが、それをベースに新たな確認書を取り交わします。法定職場では、労基法に基づく36協定を、それ以外の職場では協定に準じた内容の「確認書」を取り交わすことで大枠は合意しました。
2月10日自治研集会を開催

2月10日、木曽町の郡民会館で、長野県職労地方自治研究集会を開催しました。9月の御嶽山の噴火災害による観光を中心とした地域産業への影響が出ているため、復興支援としても位置付け、木曽での開催としました。おかげさまで100名を超える皆さんに参加いただき、集会は成功裏に終わりました。県の機関で働く県職労組合員だけではなく、木曽地域の自治体に派遣されている県職員(組合員)、木曽地域の自治体で働く自治労組合員・地域おこし協力隊員の皆さんにもご参加いただき、それぞれの立場・視点でのご意見をいただくことができました。レポート発表など集会のためにご尽力いただいた皆さんに感謝申し上げます。
午前中は、福島大学教授の今井照先生から「人口減少社会を考える」と題して基調講演をいただきました。「地方消滅」論の背景、原発災害避難自治体の状況と、そこから見えて来るこれからの自治体の役割などについてお聴きすることができました。午後は、分散会でレポート発表を受けての意見交換、木曽福島の会場周辺のフィールドワークの二組に分かれての活動になりました。
幸い珍しく?晴天に恵まれましたが、戸外では日没の早さと厳しい冷え込みも体感することができました。私たち県の仕事では、直接住民の方と接する業務に従事している職員は少数かもしれませんが、今私たちには何を求められているのか、何ができるのか・何をしなければいけないのかを考える・行動するきっかけになれば幸いです。それぞれの立場で参加いただいた皆さんに感謝申し上げます。また、夜の交流会にも約70名の方が参加いただきました。更に議論が深まったのではないでしょうか。全体交流会の後も、それぞれ地域経済のためにご努力いただいたことと思います。ありがとうございました。